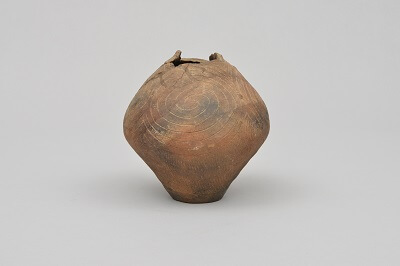もくぞうみょうけんそんりゅうぞう
木造妙見尊立像
妙見尊は星を神格化したものだそうです。何という星でしょう?
こちらのほおが自然にゆるんでしまうほどかわいらしい木造妙見尊立像です。ふっくらとした幼い童のお顔に似合わず右手に宝剣、左手にはヘビを持って立っていらっしゃる。それもカメの上に乗りながら!
勇ましさと幼さを合わせ持った木造妙見尊立像は、妙見菩薩とも言われ、北極星もしくは北斗七星を神格化したものと考えられています。童の姿もあれば、武人のような見た目だったりなどさまざまな姿で造られているようです。
この木造妙見尊立像は正面からの姿もいいのですが、横からの姿がまた素晴らしい。後ろに長く垂れた黒髪が彩色されたきらびやかな衣にかかる様子や、カメの長い首がニョキっと立ち上がっているところに、生き生きとしたものを感じます。見る角度によって雰囲気が変わる仏像です。
勇ましさと幼さを合わせ持った木造妙見尊立像は、妙見菩薩とも言われ、北極星もしくは北斗七星を神格化したものと考えられています。童の姿もあれば、武人のような見た目だったりなどさまざまな姿で造られているようです。
この木造妙見尊立像は正面からの姿もいいのですが、横からの姿がまた素晴らしい。後ろに長く垂れた黒髪が彩色されたきらびやかな衣にかかる様子や、カメの長い首がニョキっと立ち上がっているところに、生き生きとしたものを感じます。見る角度によって雰囲気が変わる仏像です。
解説
妙見尊は一般的に妙見菩薩と称され、北斗七星中の主星である北辰を最勝星とし、これを尊星王または妙見菩薩として崇拝する。この菩薩は国土を擁護し、災害を滅し、国難を滅除することを誓願するといわれる。
平安時代の中期から関東に勢力をはった桓武平氏の間には、妙見信仰が強く普及していた。源頼朝による文治5年(1189)奥州合戦の論功のひとつとして、千葉常胤が好島荘の預所職を授けられた。正治2年(1200)には常胤四男である大須賀胤信がこの預所職を引き継ぎ、大須賀氏が当地方に移住するに従って、妙見信仰も移されたものとみられる。
春日厨子に安置された御尊像は、丸頭でりりしい目鼻だちの童子形である。童直衣 を着し亀の背に立ち、右手には宝剣、左手には蛇体を持ち、背には円光背を負っている。着衣には宝相華唐草の彩色があり、端厳温雅な表現である。
作者は不明であるが、鎌倉時代末の制作とみられ、妙見信仰の歴史的資料となるべきものである。
なお本像は、明治初年に廃寺になった真言宗薬王寺の末寺であった妙見寺の所有仏であった。
平安時代の中期から関東に勢力をはった桓武平氏の間には、妙見信仰が強く普及していた。源頼朝による文治5年(1189)奥州合戦の論功のひとつとして、千葉常胤が好島荘の預所職を授けられた。正治2年(1200)には常胤四男である大須賀胤信がこの預所職を引き継ぎ、大須賀氏が当地方に移住するに従って、妙見信仰も移されたものとみられる。
春日厨子に安置された御尊像は、丸頭でりりしい目鼻だちの童子形である。童直衣 を着し亀の背に立ち、右手には宝剣、左手には蛇体を持ち、背には円光背を負っている。着衣には宝相華唐草の彩色があり、端厳温雅な表現である。
作者は不明であるが、鎌倉時代末の制作とみられ、妙見信仰の歴史的資料となるべきものである。
なお本像は、明治初年に廃寺になった真言宗薬王寺の末寺であった妙見寺の所有仏であった。
- 指定区分
- 県指定
- 種別
- 重要文化財(考古資料)
- 住所
- いわき市四倉町字西三丁目
- 施設名
- 妙見堂
- 指定年月日
- 昭和30年12月27日