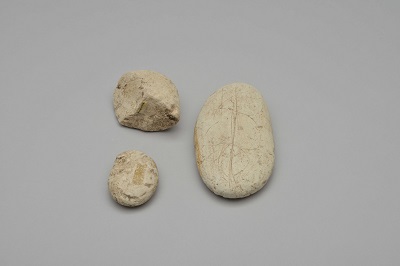こんどうそうあかうるしぬりおい
金銅装赤漆塗笈
かわいらしいアヤメの模様があります。どこにあるでしょうか?
金銅板で装飾された山伏笈です。作られた当時は赤うるしで塗られていたと考えられています。
山伏笈とは、山で修行する人々が仏具、衣類、食器などを入れて移動する際に背負う足付きの箱を言います。さながら現代のリュックサックといったところでしょうか。
リュックサックと考えれば、このように手の込んだデザインではなくても使用に問題はないわけです。しかしここには大切なお経も入れるわけですから、それに見合うように赤うるしで塗り、金メッキ加工された金銅板でさまざまに飾られました。
中でも鈴の部分にとても小さな粒で一面を彫った中に描かれたアヤメはたおやかで美しい。
他の装飾部分もとても細かく模様が刻まれているので、ぜひ、画像を目一杯拡大してみていただきたいです。
山伏笈とは、山で修行する人々が仏具、衣類、食器などを入れて移動する際に背負う足付きの箱を言います。さながら現代のリュックサックといったところでしょうか。
リュックサックと考えれば、このように手の込んだデザインではなくても使用に問題はないわけです。しかしここには大切なお経も入れるわけですから、それに見合うように赤うるしで塗り、金メッキ加工された金銅板でさまざまに飾られました。
中でも鈴の部分にとても小さな粒で一面を彫った中に描かれたアヤメはたおやかで美しい。
他の装飾部分もとても細かく模様が刻まれているので、ぜひ、画像を目一杯拡大してみていただきたいです。
解説
上釜戸清谷寺に伝来する金銅装笈は、赤漆塗の山伏笈で、各種の技法による文様・器物などを表現した金メッキを施した厚手の金銅板で飾られている。
上部の山形は、金覆輪をつけ、日月を表現する。五条の框には各々古風な猪目透しがある八双金具の外に、魚子地に唐草文・仏具・海棲動植物を毛彫り打ち出しで表現する。最上段の框には「南無阿弥陀仏」の6字の名号を表現する。上段の扉は右を欠失するが、左には風鐸をつけた三重塔と菱花文の蝶番金具をとりつける。ケンドン板には蓮華にのる輪宝を並置し、帖木には蓮台上の三鈷柄剣、下に三鈷鈴を表し、鈴にはアヤメを魚子地で現わす。往時は赤漆地に、華麗な金銅金具が美しく輝いていたと思われる。
背面には次の銘文が墨書され、中央に釈迦如来を表す梵字がある。「奉納 法花妙典 陸拾六部」左右に「拾羅刹女 上州之住眞如房」「三十番神 天正貳年甲戌拾月吉日」とあり、さらに梵字・不明文字仮名交り文がある。納人物は「三部之秘経」と墨書した経箱の断片がある。
天正2年(1574)は奉納日であるので、笈の制作はさらに古い。近似するものに、永享2年(1430)の山形県慈恩寺禪定院の笈がある。これをもとに推測すると、清谷寺笈は室町時代前期ごろの制作とみられ、山伏笈中古期に属するものである。
上部の山形は、金覆輪をつけ、日月を表現する。五条の框には各々古風な猪目透しがある八双金具の外に、魚子地に唐草文・仏具・海棲動植物を毛彫り打ち出しで表現する。最上段の框には「南無阿弥陀仏」の6字の名号を表現する。上段の扉は右を欠失するが、左には風鐸をつけた三重塔と菱花文の蝶番金具をとりつける。ケンドン板には蓮華にのる輪宝を並置し、帖木には蓮台上の三鈷柄剣、下に三鈷鈴を表し、鈴にはアヤメを魚子地で現わす。往時は赤漆地に、華麗な金銅金具が美しく輝いていたと思われる。
背面には次の銘文が墨書され、中央に釈迦如来を表す梵字がある。「奉納 法花妙典 陸拾六部」左右に「拾羅刹女 上州之住眞如房」「三十番神 天正貳年甲戌拾月吉日」とあり、さらに梵字・不明文字仮名交り文がある。納人物は「三部之秘経」と墨書した経箱の断片がある。
天正2年(1574)は奉納日であるので、笈の制作はさらに古い。近似するものに、永享2年(1430)の山形県慈恩寺禪定院の笈がある。これをもとに推測すると、清谷寺笈は室町時代前期ごろの制作とみられ、山伏笈中古期に属するものである。
- 指定区分
- 県指定
- 種別
- 重要文化財(工芸品)
- 住所
- いわき市常磐藤原町手這50-1(いわき市考古資料館)
- 施設名
- 清谷寺
- 指定年月日
- 昭和59年3月23日