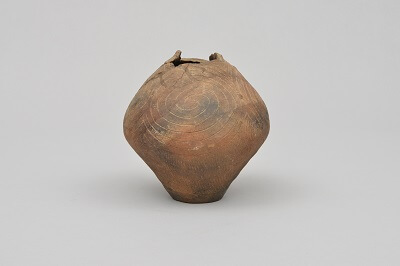らいでんめん
雷電面
こめかみのあたりに模様があります。何の模様でしょうか?
こんな形相で睨まれたら背筋が凍ってしまうんじゃないかと思うほど迫力に満ちた面です。くるっと横にしてみると、キュッと上がった頬骨や噛み付かんばかりに牙を見せる口元に、彫りの素晴らしさを見ることができます。画像を少し拡大すると、こめかみあたりにくるくると細く彫られた髪の毛があり、改めて技巧の高さを感じることでしょう。
幕府お抱面打師大野出目家4代目の力が発揮された作品です。
幕府お抱面打師大野出目家4代目の力が発揮された作品です。
解説
雷電は、能の演目の5番目物に属し、その筋は次のとおりである。
延暦寺の座主法性坊の律師僧正が、天下の御祈祷のため百座の護摩をたいていた満願の日の夜更けに、中門の扉をたたく者がいた。良く見れば、筑紫で果てたと聞いた菅 丞相(菅原道真)であった。丞相の語るには、この世で果し得なかったうらみを雷電となって内裏に飛び入り、我に憂き目を見せた者達を蹴殺すから、その時僧正は召されても参内されないようにと告げ、鬼神の相をあらわし姿を消した。
やがて紫宸殿の上に黒雲が覆い、雷鳴四方にとどろき、内裏が漆黒の闇となったとたんに雷電が姿をあらわし、うらみの公卿達におそいかかり、荒れ狂い、王城も危うく見えたが、僧正の祈る数珠でおさまるという。この能のシテ雷電が用いる面である。
この雷電面は檜材を用い、彩色してある。炯々たる金色の両眼、さかだつような眉、口をかっと開き朱の舌を出し、牙をむき出した形相は鬼気せまるものがあり、鬼神の相を如実に表現している。色彩が巧みで毛描きの妙は驚くばかりである。裏面にはつぎの刻銘がある。
万治三庚子年 奉掛 御宝前 正月吉日岩城菊田郡下川村 水野谷加兵衛作
この面は大野出目家4代の出目洞白が、水野谷加兵衛と称していた万治3年(1660)1月に出羽神社に奉納したもので、津神社の翁面より4ヵ月後の作である。ともに洞白壮年期の優れた作品である。
延暦寺の座主法性坊の律師僧正が、天下の御祈祷のため百座の護摩をたいていた満願の日の夜更けに、中門の扉をたたく者がいた。良く見れば、筑紫で果てたと聞いた菅 丞相(菅原道真)であった。丞相の語るには、この世で果し得なかったうらみを雷電となって内裏に飛び入り、我に憂き目を見せた者達を蹴殺すから、その時僧正は召されても参内されないようにと告げ、鬼神の相をあらわし姿を消した。
やがて紫宸殿の上に黒雲が覆い、雷鳴四方にとどろき、内裏が漆黒の闇となったとたんに雷電が姿をあらわし、うらみの公卿達におそいかかり、荒れ狂い、王城も危うく見えたが、僧正の祈る数珠でおさまるという。この能のシテ雷電が用いる面である。
この雷電面は檜材を用い、彩色してある。炯々たる金色の両眼、さかだつような眉、口をかっと開き朱の舌を出し、牙をむき出した形相は鬼気せまるものがあり、鬼神の相を如実に表現している。色彩が巧みで毛描きの妙は驚くばかりである。裏面にはつぎの刻銘がある。
万治三庚子年 奉掛 御宝前 正月吉日岩城菊田郡下川村 水野谷加兵衛作
この面は大野出目家4代の出目洞白が、水野谷加兵衛と称していた万治3年(1660)1月に出羽神社に奉納したもので、津神社の翁面より4ヵ月後の作である。ともに洞白壮年期の優れた作品である。
- 指定区分
- 市指定
- 種別
- 有形文化財(彫刻)
- 住所
- いわき市泉町下川字神山前
- 施設名
- 出羽神社
- 指定年月日
- 昭和48年6月30日