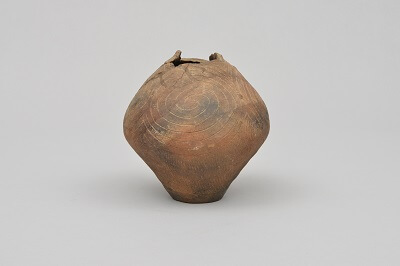もくぞうもんじゅぼさつきしぞう
木造文殊菩薩騎獅像
文殊菩薩は何を司る菩薩でしょうか?
うわあ、かっこいい。と、思わず声がもれてしまう木造の文殊菩薩と獅子の像です。文殊菩薩は智慧(ちえ)を司る菩薩であり、本来は右手に剣、左手にお経の巻物を持っていたと考えられます。思慮深く、それでいてさわやかな表情を見ると心がひきつけられ、水晶で作られた玉眼の眼差しは涼やかで吸い込まれてしまいそう。
この像は正面から見た姿も十分素晴らしいのですが、ぜひとも側面から見ていただきたい。獅子の毛の流れやたくましい脚、今にもシャラシャラと揺れる音が聞こえてきそうな素晴らしい文殊菩薩の宝冠などの造形美が感じられます。また獅子の後ろ姿は非常にチャーミングで、カッと口を大きく開いた勇ましさとは違ったかわいらしさがあります。
もとは極彩色だったようですが、今でも見どころ満載の獅子像です。
この像は正面から見た姿も十分素晴らしいのですが、ぜひとも側面から見ていただきたい。獅子の毛の流れやたくましい脚、今にもシャラシャラと揺れる音が聞こえてきそうな素晴らしい文殊菩薩の宝冠などの造形美が感じられます。また獅子の後ろ姿は非常にチャーミングで、カッと口を大きく開いた勇ましさとは違ったかわいらしさがあります。
もとは極彩色だったようですが、今でも見どころ満載の獅子像です。
解説
薬王寺は磐城の古刹で、新義真言の道場として中世に最も盛んであったが、明治元年(1868)の兵火にあい、堂宇・仏像・仏具等の多くが失われた。この像は、磐城平藩主・内藤義孝が元禄16年(1703)に、二十世日元法印のもとに寄進したものと伝えられている。
文殊菩薩は大智と大悲の力をそなえて、諸菩薩の最上位をしめ、清涼山に住み、仲間である諸菩薩1万人に説法したという。象に乗った普賢菩薩とともに、釈迦如来の脇侍を構成しているが、独立した一尊像として経蔵に安置されることが多く、本像も元々経蔵に安置されていた。本来は右手に剣、左手に経巻を持っていたと思われるが、持物は失われ、獅子の背の蓮華座に趺坐している。なでつけるような髪型や衣服の形式は宋朝様式を表わし、やや写実的なスタイルは清潔ですっきりとした美しさを示している。大智を表現した理智的な尊顔は「文殊の知恵」の形容詞にもふさわしく、眼には玉眼が入っている。
筋肉の隆々たる四肢を台座に運び、左方斜に構える獅子の雄姿は口を開き力強く、もとは極彩色であったと思われるが、今は口の中に朱色を残すのみで、すべて剥げ落ちている。鎌倉時代末期の作と思われる。
文殊菩薩は大智と大悲の力をそなえて、諸菩薩の最上位をしめ、清涼山に住み、仲間である諸菩薩1万人に説法したという。象に乗った普賢菩薩とともに、釈迦如来の脇侍を構成しているが、独立した一尊像として経蔵に安置されることが多く、本像も元々経蔵に安置されていた。本来は右手に剣、左手に経巻を持っていたと思われるが、持物は失われ、獅子の背の蓮華座に趺坐している。なでつけるような髪型や衣服の形式は宋朝様式を表わし、やや写実的なスタイルは清潔ですっきりとした美しさを示している。大智を表現した理智的な尊顔は「文殊の知恵」の形容詞にもふさわしく、眼には玉眼が入っている。
筋肉の隆々たる四肢を台座に運び、左方斜に構える獅子の雄姿は口を開き力強く、もとは極彩色であったと思われるが、今は口の中に朱色を残すのみで、すべて剥げ落ちている。鎌倉時代末期の作と思われる。
- 指定区分
- 国指定
- 種別
- 重要文化財(彫刻)
- 住所
- いわき市四倉町薬王寺塙
- 施設名
- 薬王寺
- 指定年月日
- 明治39年4月14日